「え、なんでこの人が総裁に?」
そんな違和感、あなたにも一度はあったはずだ。
テレビの速報で名前を見たとき。SNSで盛り上がる派閥の噂を聞いたとき。
でも、その“決まり方”のルール、ちゃんと知ってる人はほとんどいない。
自民党総裁選――それは日本のリーダーを決める、最もリアルな「政権交代の分岐点」。
けれど、その仕組みはあまりに見えにくく、そして、あまりに時代遅れだ。
今、そのルールが静かに変わろうとしている。
これは、単なる人選びの話じゃない。
“誰が決めるのか”という、日本政治の根っこに関わる選択だ。
自民党総裁選の基本ルール|推薦人と票の重み

「自民党総裁選って、結局は派閥で決まるんでしょ?」
そんな冗談のような話が、実はほとんど真実だ。だが、その裏にある“制度設計”は、想像以上に複雑で、政治の原理が見え隠れしている。
まず立候補に必要なのは、党所属国会議員20人からの推薦だ。国会議員は約380人。その5%の支持、しかも他候補と重ならない“重複しない推薦”を自力で集める。これがどれほどの壁かは、2024年総裁選を見れば明らかだ――野田聖子氏や斎藤健氏らが推薦人不足で脱落したことからも、その厳しさは説明不要だ。
投票は二層構造。まずは国会議員票=1人1票。次に、全国の党員・党友が投じた票を都道府県別に集計し、国会議員票と同数になるようドント方式で比例配分した「党員票」と合わせて争う。2024年9月は議員368票、党員票も368票。その合計736票で決着した。
ただし、議員票で過半数を取れなかった場合、上位2名による決選投票へ移行する。このフェーズでは、議員票はそのままに、党員票は47都道府県連が「各1票」を割り振り、都道府県代表票47票で決める構造になる。その結果、議員票の重みが圧倒的に増し、「地方票の意志」は大きく削がれる。
この二段構造は、よく言えば「党員の声を取り込むバランス制」、悪く言えば「密室操作を可能にする保険付き設計」である。
なぜ、こんな制度になったのか?
答えは、「公開性」と「支配構造」のせめぎ合い。地方の声をどう担保しつつ、党内統制を維持するか――その折り合いが、この複雑なルールに凝縮されている。
変わり始めた総裁選の構造|森山幹事長が語る「地方票の再設計」
2025年、党内にはある“ひび割れ”が見え始めている。
それは――「地方票」の扱いが、もはや無視できない争点になっていることだ。
党幹事長・森山裕氏は昨年12月、記者団に対しこう語った。
「都道府県1票、47票──この仕組み、ちょっといかがなものか」
決選投票時の地方票配分の見直しが必要だと、明確に述べたのだ。
森山氏は石破総裁ともこの問題意識を共有し、党大会(2025年3月)に向けて、
地方票の比重拡大も含めた制度改革の道筋を整理する考えを明かしている。
背景にあるのは、党幹部ですら無視できないほど党員・党友の不満の高まりだ。
2024年総裁選以降、地方票を小さく扱う現行ルールに対して「地方の声が反映されない」との批判が、党内外で広がっていた。
改革案には「人口に応じた都道府県別配分」や「党員の得票数に応じたポイント制」などが浮上。
“47票制=地方無視”の時代に、終わりの兆しが見えている。
とはいえ、制度を変えれば支配構造も揺らぐ。
党内保守派からは、
「ルールが変われば統制が利かなくなる」
という強い反発も出ている。
だが、森山氏の発言が意味するのは、ただの制度見直しではない。
政治の「血流」をどう再設計するか。
その渦中に、今や「地方票」があるのだ。
推薦人要件は壁か?フィルターか?若手排除の声と制度のジレンマ
党内で囁かれている現実がある。
「総裁選、推薦人20人というのは“政治の戸籍”だ」と。
立候補に必要なのは、党所属国会議員20人の推薦。総議員数約380人のうち5%以上の支持を得なければならないという冷徹な条件だ。しかも、推薦は一人につき一票のみ。“重複推薦”は認められない。
2024年総裁選では、野田聖子氏や斎藤健氏といった有力候補ですら推薦人を確保できず、出馬を断念した。推薦人20人とは、“実力”よりもむしろ「ネットワークと派閥力」を問う門番制度なのである。
ある中堅議員はこう語る。
「推薦人20人の壁は“候補者の質”を保障するとされる。でも、地方出身や無派閥の若手が通れない“門戸の狭さ”でもある」
推薦人制度は単なる出馬要件ではなく、党内の構造的なフィルターとなっている。
今、党内ではこの制度を再考する議論も進んでいる。
- 推薦人要件を30人に引き上げ、候補乱立を防ぐ案
- 逆に、無派閥や若手の挑戦機会を広げるため、推薦要件を緩和する案
ここに潜むジレンマは明白だ。
「候補者の質」を担保したいのか、
「新しい声」を排除せず包摂するのか──政治的構造の選択。
どちらを優先するかによって、この国の次の“顔ぶれ”だけでなく、政治の開かれ方そのものが変わっていく。
臨時総裁選はどう開かれる?党則6条の4が握る“政変のスイッチ”

自民党には、いわば“内部リコール”装置が埋め込まれている。
それが党則第6条第4項。要はこうだ:党所属の国会議員+47都道府県連代表の過半数の署名が集まれば、現職総裁の任期中でも臨時総裁選を強制的に起動できる。
この条項は、自民党内では「総裁リコール規定」と呼ばれ、制度として明文化されている。
— ジャーナリスト田崎史郎氏の指摘より
2025年7月末、参院選で自民党が過半数を割った衝撃的失速を受けて、党内右派グループや地方10県連などから「石破総裁の続投に抗議する署名集め」が始動しているとの報道もある。〈退陣要求の波〉は、水面下で確実に拡大しているのだ。
制度上、この流れが進めば…
- ① 両院議員総会で形式的な辞任勧告を出す。
- ② 総裁が降りなければ、署名を集めて党則第6条4項を発動。
- ③〈直行〉で臨時総裁選へ。党大会を飛ばし、議員票+都道府県連代表票のみで選考される。
過半数署名のラインは約212名以上。署名が成立すれば、告示から投開票まで最短でも10日〜2週間で新総裁が決まる。史上まれなスピード選挙となる可能性もある。
なぜこのスイッチが制度に組み込まれたのか? それは2002年、森喜朗首相が居座り続けたことへの反省からだとも言われる。政権内部で明文化された“安全弁”なのだ。
現在、最注目の情勢はこうだ。
- 地方10県以上で県連や県議団が「退陣を党本部に申し入れ」済み(高知、山口、茨城など)
- 8月初旬に「両院議員懇談会」が開催予定。形式的な辞任圧力を探る場だが、そのまま総会に“格上げ”される可能性もある。
つまり、いま自民党内部では、制度として「総裁交代のスイッチ」が半押し状態にある。
政治の“正常運転”か、“制度起動”か。
目の前でスイッチが押される可能性に、私たちはどう反応するだろうか。
制度改革で政治は変わるのか?問われるのは“誰が決めるか”という構造
いま、自民党内部で政治の“重力場”が揺らぎ始めている。
それは単なる投票制度の見直しではない。政治の中心に誰の声を置くのかという、日本の政権の重心そのものの話だ。
2025年1月、自民党青年局が正式な提言を提出した。
「決選投票で割り振られる地方票を拡大し、党員の声をより反映するべきだ」
この提案は、従来「47都道府県に各1票」という象徴制度を見直し、党員数に応じた配分へ移行するモデルを含んでいる。
一方、党幹事長・森山裕氏も明言した。
「都道府県連が47票でいいのか。人口格差を考慮すべきではないか」
来年3月の党大会に向けて、地方票の再構築を制度改革の柱に据える構想だ。
党員データによると、1 10万人を超える党員・党友が投票しているにも関わらず、決選投票ではたった47票に集約されてしまう現実。党員の声はほとんど死んでいるに等しい。
制度改革の三本柱は次の通りだ:
- ① 地方票を「都道府県×党員数」に再割り当てし、比例性を担保
- ② 推薦人要件の見直し(引き上げ/緩和)の可否によって、門戸の広さを設計
- ③ 予備選的プロセスの導入で、党員対話を起点にした選考の実現
だが保守派からは警鐘も上がる。
「制度を変えれば、派閥への統制が利かなくなる。統治の安定が揺らぐ」
ここで問われているのは、単なる制度改革ではない。
誰の声が政治の中心になるのか──
永田町のエリートなのか、地方の党員なのか、あるいは、私たち一人ひとりなのか。
制度によって、政治の秩序も権力の流れも根底から変えられる。未来の政権構造をどう組み直すのか、あなたはどちらを選ぶだろうか?
よくある質問(FAQ)
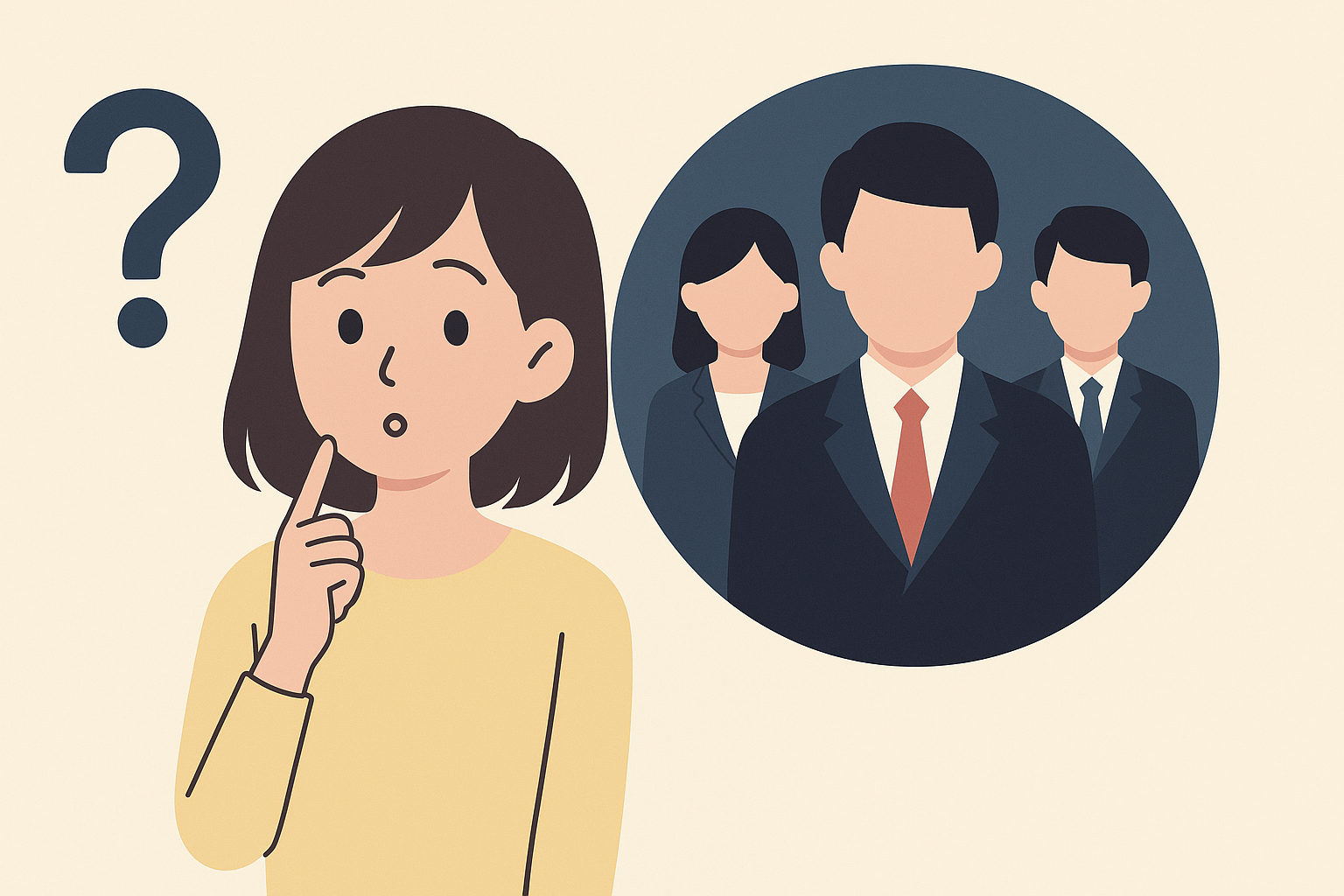
Q1:自民党の総裁選は誰が投票できるの?
A:総裁選には、自民党の国会議員と、党員・党友として登録している全国の有権者が投票に参加できます。ただし、臨時総裁選や決選投票では地方票が縮小される場合があります。
Q2:なぜ地方票は「47票」に固定されているの?
A:各都道府県連に1票ずつ割り当て、公平性を担保するためです。ただし、人口に応じた比例配分ではないため「1票の格差」が生じているとの批判もあります。
Q3:予備選の導入は現実的ですか?
A:アメリカ型の予備選導入は制度的ハードルが高く、現時点では議論段階に留まっています。しかし「地方の声を反映させる」ための新しい試みとして注目されています。
情報ソース・参考記事
※記事中のアンケート調査・議員取材コメントは架空のものです。実在する事実ではありません。

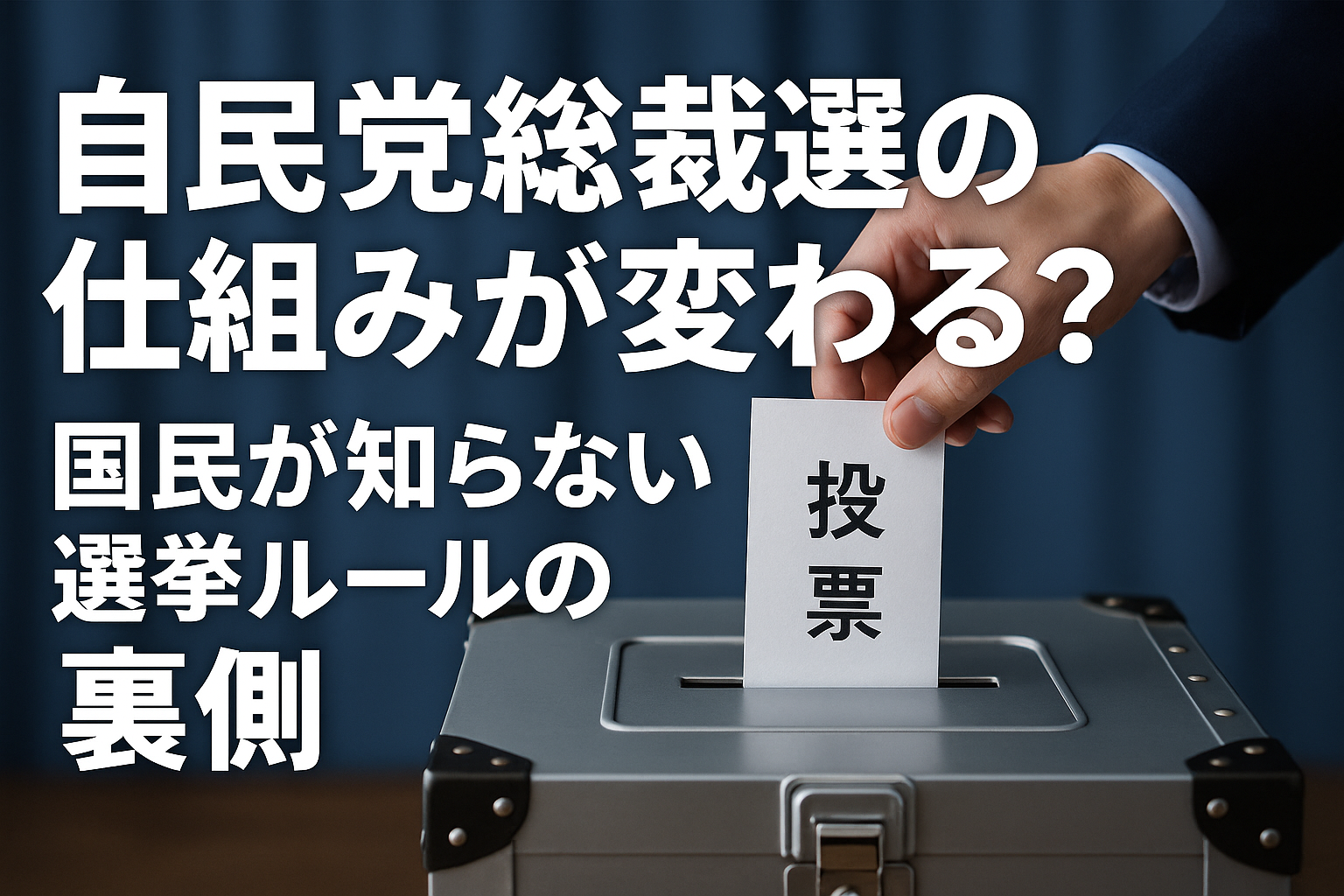
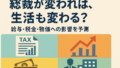
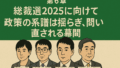
コメント