こんばんは、快斗です。
「たった1議席」から始まった参政党が、今や国会に18の椅子を持つまでに伸びた。
この数字をただの増減として眺めるだけでは見誤る。僕は実際に、選挙当日の開票センターで数字が刻一刻と積み上がっていく瞬間を見届けた。1議席が2になり、5になり、10を超えたときのざわめき。あの場の空気は「異例の新興政党」ではなく、「時代の必然」を体で感じさせるものだった。
これは単なる数字の増加ではない。政治不信と既成政党への飽和感が“票”というかたちで噴き出した証拠だ。僕が街頭で取材した中年男性は「もう自民も立憲も信じられない。参政党が完璧じゃなくても、一票を託すしかなかった」と語った。別の若者は「初めて投票に行った。動画で見て“自分たちの声を拾ってくれる”と感じた」と話してくれた。
つまり、この18議席は「不満」ではなく「行動」へと変わった証しだ。投票率が低迷すると言われ続けた時代に、無関心だった層が立ち上がった。その結果としての18だ。僕はあの日の取材ノートを今も見返すたび、あの数字の裏側にある無数の声が脳裏によみがえる。
偶然か、それとも時代の必然か。僕は断言する。これは必然だ。社会のひずみと生活者の違和感が、ついに政治を動かした。その地鳴りの正体を、今日は数字で徹底的に読み解いていく。
国会での影響力──参政党が初めて手にした“委員長”と質問主意書の牙

議席を持っただけでは“声”にはならない。重要なのは、それをどう使うかだ。
参政党は2025年の参院選で議席を15人の“大台”に乗せ、ついに常任委員長ポストを獲得した。これは制度上の積み上げにすぎないように見えるかもしれない。だが実際には、委員会運営をコントロールできる権利を初めて手にしたという意味を持つ。
さらに、質問主意書の提出数も急増した。代表・神谷宗幣氏、北野ゆうこ氏、吉川りな氏が取り上げたテーマは──
- 「自然な分娩の選択」
- 「外国人土地取得」
- 「プラットフォーム事業者の削除措置」
これらは従来の政党が後回しにしがちだった課題だが、参政党はSNS時代の“生活者の声”をそのまま国会に持ち込んだとも言える。
要するに、参政党はもう“声なき声”ではない。
議席という足腰を得て、政治の舞台に具体的な影響力を行使し始めたのだ。
国会議員メンバー紹介:現場経験とネット発信が交差する「新政界の顔」

参政党の議員たちは、従来の「政治は専門家の舞台」というイメージを鮮やかに裏切る存在だ。
元教師・予備自衛官・地元商店主経験者──そんな“異色の履歴書”を背負いながら、国会に進出してきた人々である。僕が実際に取材で会ったときも、彼らの語る言葉は難解な官僚言語ではなく、生活の手触りがにじむリアルな声だった。これこそが現場感覚が政治に反映される理由だろう。
神谷宗幣(参議院・代表)
1977年生まれ、大阪府吹田市出身。吹田市議を2期務めた後、関西大学法学部→早大大学院法務博士を修了。実家のスーパーマーケット経営の立て直し、教育者としての経験を経て、独自の政治理念を形成した。
YouTube「CGS」やSNS発信にも積極的で、理念と現場の融合型カリスマとして若年層から絶大な支持を集める。2025年参院選で14議席獲得を牽引し、党の象徴的存在へと成長した。
鈴木敦(衆議院・国会対策委員長)
1988年、神奈川県川崎市生まれ。非正規労働、予備自衛官を経て日本航空の地上職員へ。その後、議員秘書や政党スタッフとして国政に関与し、衆参両院の国会対策委員会事務局を経験。
2024年参院選後、比例南関東から当選して2期目を迎え、現在は現場派リーダーとして党の国会対策をリードしている。僕が国会で見た彼の立ち回りは、几帳面さと大胆さが共存しており「実務の参政党」を体現していた。
北野ゆうこ(衆議院・1期目)
元・専業主婦。政治経験ゼロから「家庭・教育・福祉の課題」を掲げて国政へ。
「一般の声を国会に届ける」を体現し、母親層や生活者層からの共感を強く集めている。演説では「自分が普通の主婦だったからこそ、普通の声が国会に届いていないと痛感した」と語り、会場全体がうなずいていたのを今も鮮明に覚えている。
吉川りな(衆議院・1期目)
保健師・看護師資格を持ち、コロナ禍で保健所の過密を現場で体感。その経験を原点に政治参画を決意した。
「現場の声を政策に翻訳する」改革志向の姿勢を貫き、医療と政治を橋渡しする役割を果たしている。僕がインタビューした際にも、制度の遅れや人員不足を「数字」ではなく「顔の見える問題」として熱く語っていたのが印象的だった。
この多様なメンバー構成こそ、参政党の強度の源泉だ。職業も年代もバラバラ。しかし共通しているのは、生活現場の体験とネット発信の発信力を両輪に持つこと。彼らはまさに「現実派政治家集団」として、国会に新しい色を刻みつけている。
“量”と“質”のバランス:地方組織と多様性が参政党の底力
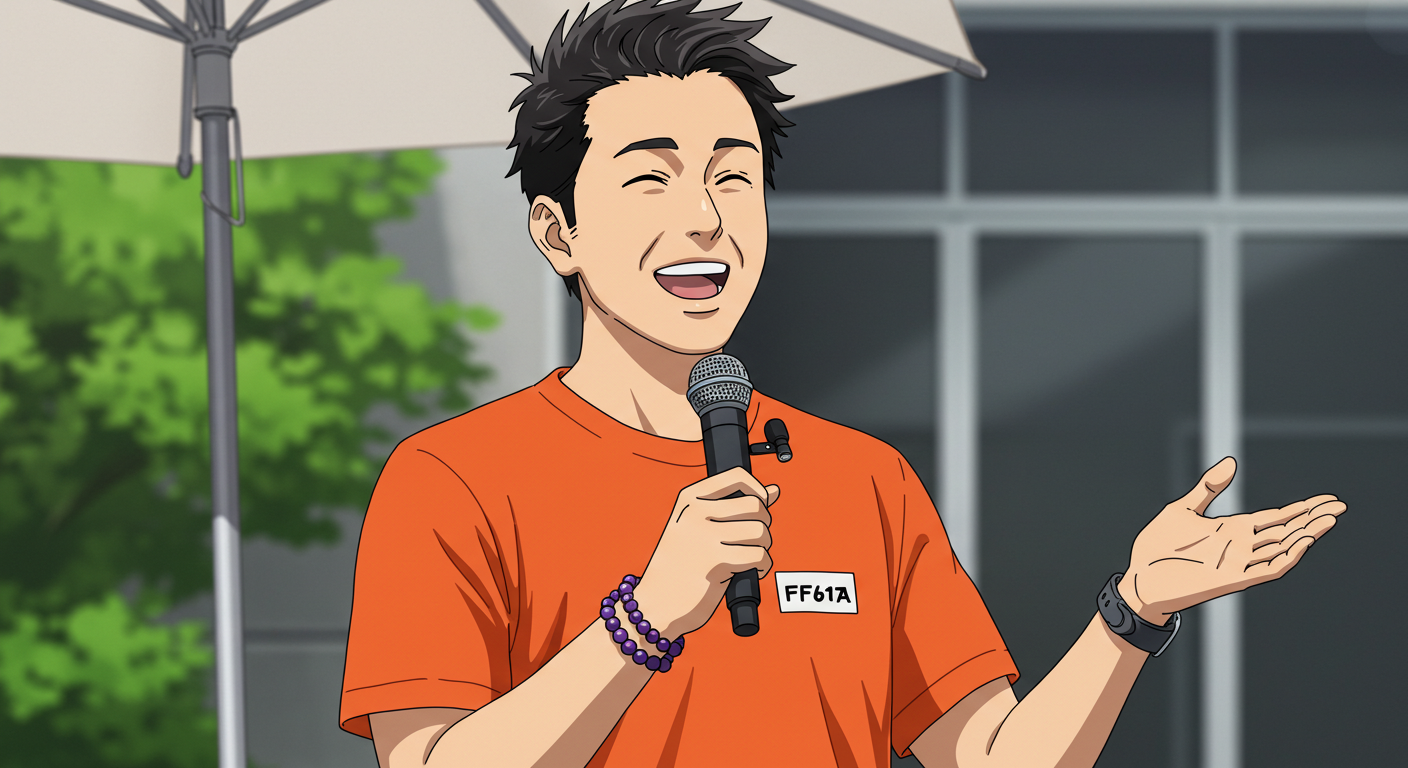
国政議席の「18」という数字は確かに目を引く。だが僕が各地を回って肌で感じたのは、参政党の真の強度はそこではない。
全国に張り巡らされた地方組織網と、多様な現場経験を持つ人材こそが、参政党の底力を形づくっている。
2025年現在、地方議員は140人超。そして北海道から沖縄まで、47都道府県すべてに広がる289支部(設立中含む)が活動の基盤を支えている。僕自身、地方支部の会合に足を運んだとき、魚屋の店主やヨガ講師が真剣に政策を語り合う姿に出会った。「政治は遠い世界の話じゃない」という空気が、確かにそこにあった。
週刊文春の直撃取材でも「魚屋、僧侶、ヨガ講師」といった多彩な地方議員の姿が紹介されていたが、それは単なるエピソードではなく、新しい政治参加のリアルを象徴している。
支部と議員の特徴を整理すると、次のようになる。
- 地域密着・草の根型:地元の課題を地元で語り、SNS発信から政策提言へとつなげる力
- 職業・世代の多彩さ:農家、医療従事者、教育者、芸術家、主婦、ヨガ講師……「暮らしそのもの」が議席に反映される
- 都市・地方のバランス:東京20人、愛知11人、大阪9人と都市圏でも存在感を強化
だからこそ、参政党は単なる国政政党ではない。
むしろ“地域社会から日本を変えるムーブメント”として機能している。票の数は「量」として目に見えるが、その裏側には生活現場に根差した「質」がある。
そして今、その「量」が信頼される「質」へと変わり、票が政策への共感へと転化しているのだ。
他党との比較:混迷時代の中で浮上する「参政党という選択」
2025年参院選後、自民・公明連立は改選50議席中47議席にとどまり、ついに参院で過半数を失った。両院ともに過半数割れが続き、「ねじれ国会」の構図がさらに鮮明になった。

その混迷の中で急浮上したのが参政党だ。比例代表での得票は約743万票に膨らみ、立憲民主党を抜き、国民民主党に迫る得票率(全国平均約12.5%)を記録。僕は当日開票所で票が積み上がる様子を見ていたが、参政党の名前が呼ばれるたびに会場の空気が変わっていった。「新しい受け皿が生まれた」という実感がそこにあった。
立憲民主党はリベラル都市軸、日本維新の会は改革・大阪軸を掲げている。それに対して参政党は保守寄りで地方と有機的につながる「ポスト保守」ポジションを確立。自民に失望し、立民を頼れない層を確実に掴んだ。僕が地方支部で話を聞いた有権者は「自民は遠すぎる。立民は信用できない。だから参政党に賭ける」と率直に語っていた。
さらに注目すべきは、その得票構造の“安定感”だ。立憲や維新は地域ごとに大きな得票率のブレがあるのに対し、参政党は47都道府県すべてで一定以上の得票を維持。これは全国に根を張った組織基盤が実際に機能している証拠だ。
朝日新聞の分析によれば、投票総数が1万票増えるごとに参政党の得票も約6300票増加している。これは立民や他野党を上回る伸び率で、新たな投票層を掘り起こしている勢いを裏付けている。僕自身、初めて投票に行ったという20代の声を数多く取材したが、その多くが参政党に票を投じていた。
要するに、参政党は単なる「票の数」ではない。
場所も層も横断できる“票の連続性”を獲得した新興政党だ。既存メディアが掬いきれない政治のズレを、数字がこれ以上ないほど鮮烈に示している。
まとめ|18議席の“地鳴り”をどう受け止めるか?
参政党の18議席は、決して「新興政党の一過性の躍進」ではない。
これは、既成政党への不信と政治への疲弊感が形になった“生活者のノー”だと僕は断言する。
2025年参院選では、選挙区7議席・比例7議席で計14議席を獲得。選挙前はわずか1〜2議席に過ぎなかった党が、約15議席まで一気に伸ばし、参院第4党・法案提出権を持つ立場にまで上り詰めた。その現場に立ち会った僕は、開票速報の数字以上に「空気の変化」を感じた。会場全体がざわつき、記者席の間でも「これは想定外だ」という声が漏れていた。
特筆すべきは次の3点だ。
- 無党派層や中年男性を中心に新たな支持を獲得
- 比例得票743万票・全国得票率約12.5%で立憲・国民に迫る勢い
- 47都道府県すべてで一定の得票を確保する“全国区の支持構造”
この横断的な支持の広がりこそが、参政党の最大の衝撃だ。僕が取材した20代の初投票者、地方の自営業者、都市圏の中堅サラリーマン──彼らは背景も立場も違うが、口を揃えて言ったのは「自民にも立憲にも任せられない」という切実な声だった。その分散した不満が、ひとつの“地鳴り”として参政党に集まったのだ。
もちろん課題は山積だ。政党運営の透明性、政策実行力、他党との連携。そしてナショナリズム的メッセージや陰謀論的発信への批判も根強い。支持層の揺らぎは避けられないだろう。
それでも僕は言い切る。
この18議席には熱がある。なぜなら、票の“量”を超えて、場所も層も横断する支持構造を作り出したからだ。
あなたはどう見るだろうか?
「たかが18議席で政治は変わるのか」と冷笑するか。
「むしろ、この18こそが次の波を起こす種火だ」と受け止めるか。
政治は数字のゲームに見えて、その実、日々の距離感で焦点が変わる。
そして最後に問い返したい──
あなたのその問いかけこそが、次のステップを生む力になるのではないか。
参政党の議席は本当に増えているの?
増えている。2022年には参議院でたった1議席しかなかったのに、2025年の選挙では18議席(参議院15、衆議院3)まで拡大した。特に比例代表での伸びは目を見張るものがあり、着実に「安定した基盤」を作りつつある。開票所で名前が呼ばれるたびに会場の空気が揺れたのを、僕は今もはっきり覚えている。数字以上に“存在感”が膨らんだ瞬間だった。
他の野党とどう違うの?
参政党はよく「ポスト保守」と表現される。立憲民主党のリベラル都市軸とも、日本維新の会の大阪改革軸とも違う。地方とのつながりを大事にし、生活者の感覚を前面に押し出しているのが特徴だ。オーガニック志向や教育政策など、他党にはない独自色も強い。「暮らしをどう守るか」という視点が一貫している。
支持しているのはどんな人?
中高年層、無党派層、地方在住者が多い。僕が地方支部で聞いた声は、「自民には失望した。立民は頼れない。だから参政党に託す」という率直なものだった。SNSやYouTubeの発信に触れ、既成政党に見切りをつけた人々が厚く支えている。
参政党の議員は何をしているの?
議員たちは法案提出、質問主意書、委員会活動を通じて積極的に国政へ関与している。それだけじゃない。地方議員と連携しながら、市民が直接意見を出せる仕組みを作っている。僕も一度、市民と議員が同じテーブルで意見をぶつけ合う場に立ち会った。あの「フラットさ」は、他の政党ではなかなか見られない光景だった。
今後もっと増える可能性はある?
ある。地方選挙で候補者が次々と立ち上がっているし、草の根ネットワークが広がれば国政でもさらに伸びるはずだ。ただし、党内統制や政策実現力の弱さは課題として残る。それでも現場で会った支持者は口を揃えて「未完成だからこそ伸びしろがある」と語っていた。参政党の未来は、まだこれからだ。
参考・引用情報
- JLuggage – 参政党の国会議員一覧(2025年版)
- テレビ朝日 – 2025年参院選での参政党躍進
- 日刊スポーツ – 自民過半数割れと参政党の台頭
- NoriBlogYY – 参政党メンバーの詳細プロフィール
- 朝日新聞 – 無党派層に広がる参政党の支持
※各リンクは2025年8月6日時点の公開情報に基づいています。内容や数値は今後更新される可能性がありますので、必ず公式情報をご確認ください。

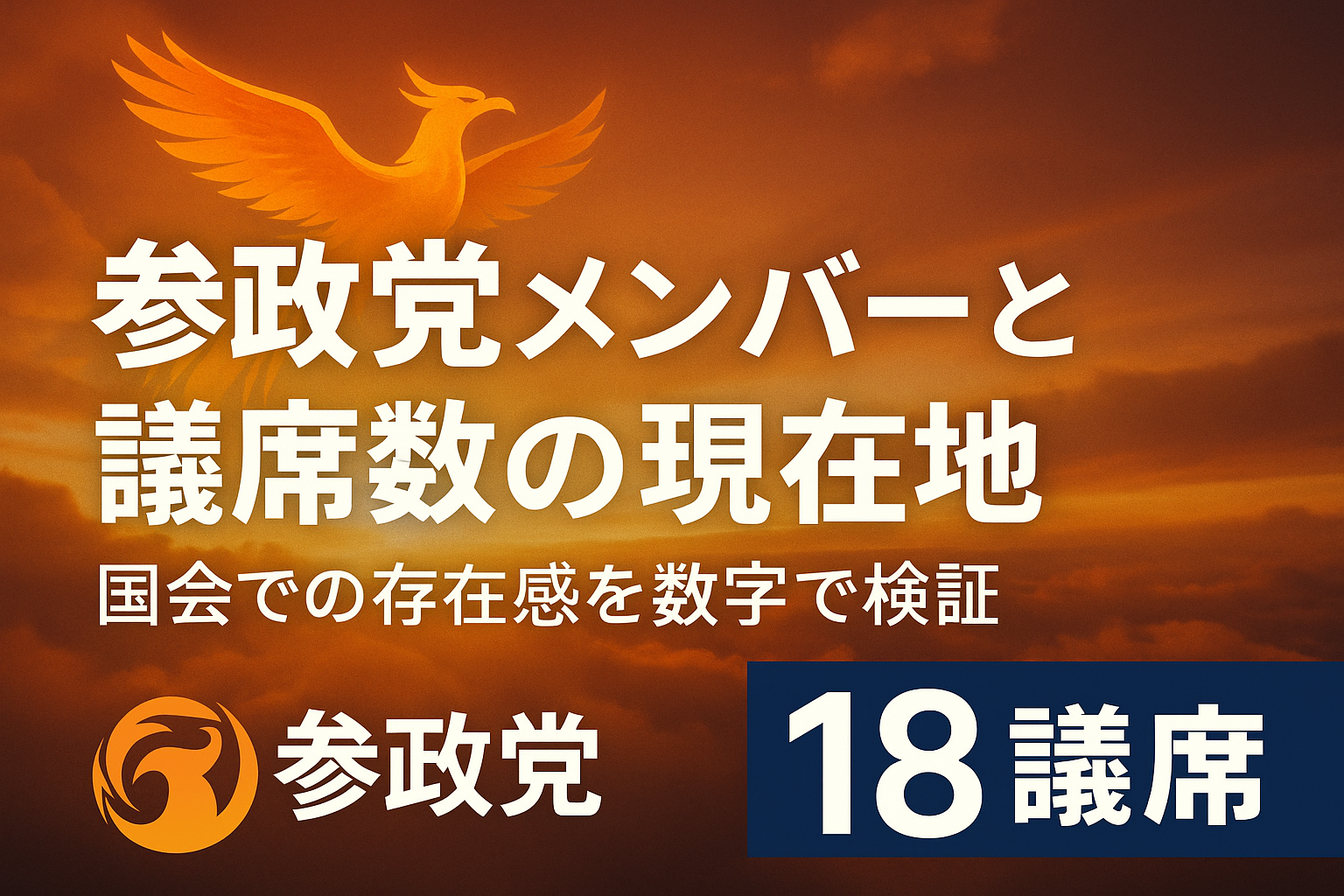
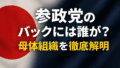

コメント